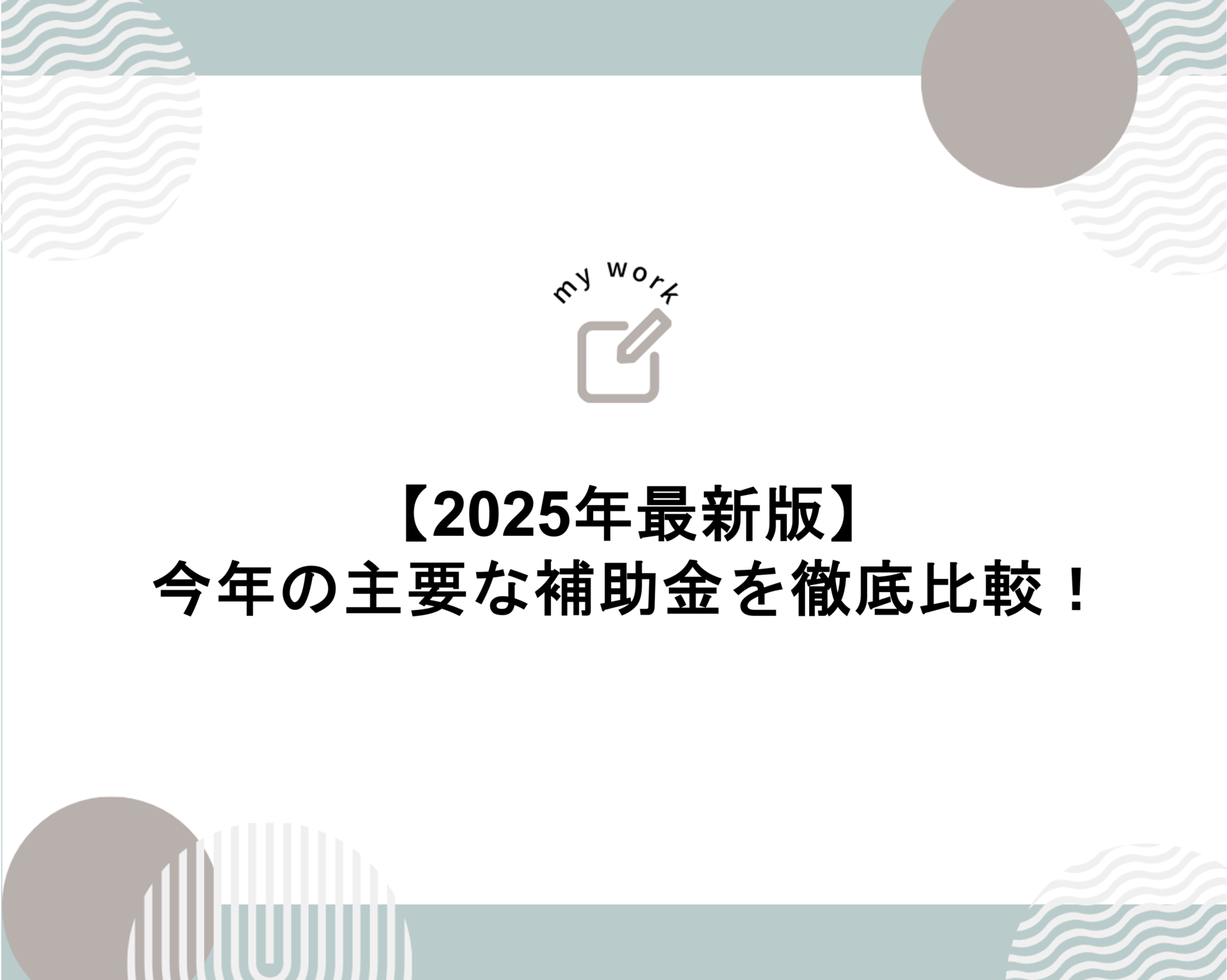こんにちは、WellFlagsです!
本日は2025年の主要な補助金徹底比較を行います。
第1章 補助金を選ぶ前に押さえておきたい基礎知識
国からもらえる支援制度には大きく「補助金」と「助成金」の2種類がありますが、それぞれの性質は大きく異なります。ここでは、その違いを整理します。
補助金と助成金の違い
- 補助金
補助金は国の政策的な目的に沿って企業の成長や新たな事業への挑戦を後押しする制度です。公募制であるため、募集期間が限定されており、限られた期間内に申請書類を提出し、審査に通過する必要があります。主に経済産業省などが所管し、イノベーションの促進や生産性の向上など、経済全体の発展に寄与する取り組みを支援する性質を持っています。審査には一定のハードルがあるものの、採択されれば返済不要の資金が得られる点が魅力です。 - 助成金
一方の助成金は、雇用や働き方の改善といった社会的課題の解決を目的に支給される資金で、主に厚生労働省が所管しています。通年もしくは長期間にわたり申請可能であり、要件を満たせば原則として支給されます。たとえば、従業員の新規雇用や職場環境の整備など、一定の条件をクリアすれば審査を経ずに支給される点が特徴です。
このように、補助金は審査を通過して受け取る支援金、助成金は条件を満たせば受け取れる支援金と覚えるとイメージしやすいです。それぞれの目的や要件に応じて使い分けることが、自社の資金調達戦略をより効果的なものにする第一歩となります。
ただし、制度によっては名称が「助成金」であっても、実態としては補助金に近い性質(審査や予算制約があるケース)を持つものも存在します。したがって、名称だけで判断せず、必ず各制度の公募要領を確認することが重要です。
補助金制度に共通する流れ
- 公募期間: 年1回のみの制度から複数回公募する制度までさまざま。
- 審査: 申請書・事業計画書を基に厳正な評価が行われ、採択率は30〜60%と幅がある。
- 後払い: まず自己資金や融資で事業を実施し、完了後に実績報告を提出して補助金を受領。
- 事後フォロー: 事業完了後もしばらく事業化状況を報告する義務がある。
制度比較で見るべき四つの観点
- 対象者: 本店・支店の登記場所の住所、業種、どのような取組かなどの要件を確認。
- 補助率と上限額: 自己負担額と特別加算の有無を踏まえ、資金計画を試算。
- 対象経費: 設備、広告費、外注費など、事業計画に沿った経費が補助対象かをチェック。
- 申請難易度と時期: 書類の量・複雑さと、公募から採択発表までのスケジュールを社内リソースと照らし合わせる。
補助金活用のメリットと注意点
メリット
- 返済不要で資金を確保できる。
- 事業計画をブラッシュアップする機会になる。
- 採択実績が対外的な信用度向上につながる。
- 専門家と連携するチャンスを得られる。
注意点
- 準備に時間と労力がかかる。
- 採択されないリスクがある。
- 補助金は後払いのため計画的に行わなければ、一時的に資金繰りが厳しくなる可能性がある。
- 実績報告や事業化報告など事後作業が必須。
| 項目 | 補助金 | 助成金 |
| 提供者 | 経済産業省が中心 | 厚生労働省が中心 |
| 受給対象・目的 | 販路開拓や新事業実施の促進 → 事業拡大を支援 | 雇用や社員の能力向上を促進 → 組織の基盤固めを支援 |
| 受給率 | 30%〜60%のものが多い | 100%のものが多い |
| 公募期間・回数 | 1年間に3〜4回程度締切 のものが多い | 通年行っているものが多い ※予算に達したタイミングで終了する場合もあり |
| 需給のポイント | 「審査に通る申請書」を考え、執筆することが重要 | 求められている情報を不備なく提出することが重要 |
第2章 目的別:主要補助金の比較一覧
| 補助金名 | 目的 | 補助上限額 | 補助率 | 主な対象経費 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓や生産性向上の取組 | 250万円 | 最大3/4 | 機械装置費、広報費、展示会費、旅費、外注費など |
| ものづくり補助金 | 革新的な製品・サービス開発 | 4,000万円 | 最大2/3 | 製造設備、システム開発費など |
| IT導入補助金 | ITツール導入による業務効率化 | 450万円 | 最大3/4 | ソフトウェア導入費、クラウド費、初期設定費用など |
| 省力化補助金(一般型) | 省力化・自動化設備による生産性向上 | 1億円 | 最大2/3 | 機械装置費、システム構築費など |
| 省力化補助金(カタログ型) | 指定ツール導入による省力化・自動化 | 1,500万円 | 1/2 | 指定カタログ掲載の自動化・省力化ツール |
| 新事業進出補助金 | 新市場・新分野への事業進出投資 | 9,000万円 | 1/2 | 機械装置費、建物費、外注費、広告費など |
近年特に賃上げ要件や地域要件など、一定の条件を満たすことで補助率が加算される補助金が増加している傾向にあります。こうした優遇措置を活用するためには、各制度の概要を正確に把握したうえで、自社の事業目的や予算計画に適合する制度を選定することが重要です。
第3章 補助金タイプ別の活用シーンとおすすめ業種
主要な補助金を抜粋して、おすすめの活用事例を以下に記載しました。
・小規模事業者持続化補助金
目的:販路開拓や生産性向上の支援
活用例:
- パンフレット・チラシの作成
- ホームページの新規制作やリニューアル
- 展示会への出展
- 店舗の改装、新商品の市場調査など
- 機械装置費(集客、生産拡大、新たなサービス提供を目的とする)
おすすめ業種:
- 小売業(店舗改装、ECサイト構築)
- 飲食業(メニュー開発)
- サービス業(HP制作)
- 製造業(展示会出展、新製品の販路拡大)
・ものづくり補助金
目的:革新的な製品・サービス開発
活用例:
- 製造機械や試験装置の導入
- 新製品を製造する機械など
おすすめ業種:
- 製造業(機械設備)
- 建設業(新サービス提供のためのシステム)
・IT導入補助金
目的:ITツールによる業務効率化・売上拡大の支援
活用例:
- 会計・給与・在庫管理ソフトの導入
- CRM(顧客管理)など
業種別導入例:
- 小売業(POSレジ・在庫管理)
- サービス業(予約・決済のオンライン化)
- 製造業(生産・品質管理)
- 建設業(見積・工程管理)
上記は業種別の活用例ですが、IT導入補助金は医療法人を含むほぼすべての業種で申請・活用が可能です。
これは、他の多くの補助金制度が医療法人を対象外としているのに対し、IT導入補助金が広範な業種を対象としている点で大きな特徴となっています。
・省力化補助金(一般型)
目的:人手不足対応・業務自動化による省力化・生産性向上の支援
活用例:
- 複数機械を組み合わせたオーダーメイド性の省力化設備の導入
- システム構築による業務効率化
おすすめ業種:
- 製造業(省力化機械導入による生産性向上)
- サービス業(受付・予約の無人化、在庫管理システムなど)
- 卸売業(受発注システムの開発)
第4章 補助金の申請難易度の違い

補助金を申請する際には、単なる申込書類の提出ではなく、事業計画書のような構成で自社の取組内容や将来性を論理的にまとめる作業が求められます。制度ごとに必要な書類の量や求められる内容の深さは異なり、準備にかかる時間や難易度にも大きな差があります。
以下では、代表的な補助金を「初級」「中級」「上級」と位置づけ、それぞれの準備や申請のボリューム感を整理してみます。
書類準備のボリューム感と難易度
IT導入補助金、省力化補助金(カタログ型)は、申請書や簡易な事業計画書、ツールの資料、決算書などを1〜2週間で準備できる「初級」です。
小規模事業者持続化補助金は、中級に位置づけられ、経営計画書や支援計画書、見積書などを1〜2か月かけて用意します。
ものづくり補助金、省力化補助金(一般型)、新事業進出補助金は上級で、技術的・市場的な裏付けを示す10〜15ページの事業計画書、定量計画、各種見積・仕様書などを2〜3か月かけて作成します。
申請前セルフチェック
自社の体制を整理し、事業計画を論理的に説明できるか、数値根拠となるデータが揃っているか、専門家のサポート体制があるか、十分な準備期間を確保できるかを確認したうえで、現実的な採択確率を見極めましょう。
第5章 補助金の併用・段階的活用という考え方
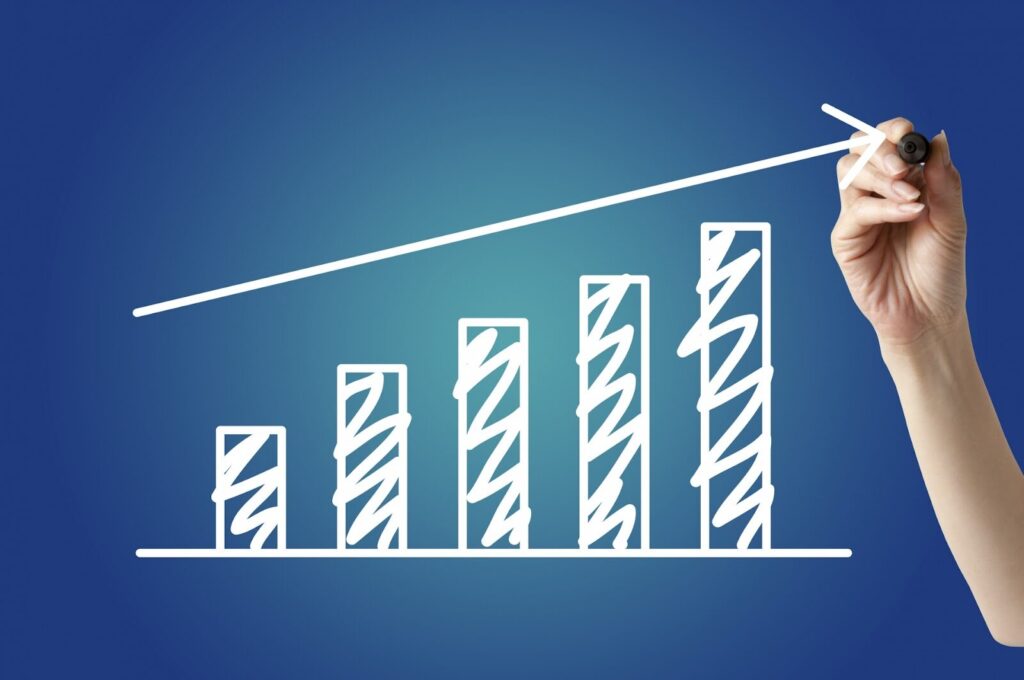
成長ステージに合わせた申請パターンと活用例を以下に記載します。
① 基盤強化 → 事業拡大型
- 短期:IT導入補助金で業務システムを整備
- 中期:持続化補助金で販路開拓・集客強化
- 長期:ものづくり補助金で本格的な設備投資
② 販路開拓 → 製品開発型
- 短期:持続化補助金で市場調査・営業強化
- 中期:ものづくり補助金で新製品を開発
- 長期:新事業進出補助金で新分野に展開
③ 事業転換・革新型
- 短期:新事業進出補助金で新規事業に転換
- 中期:IT導入補助金で業務システムを整備
- 長期:持続化補助金で販路拡大・ブランド構築
活用実例
製造業A社
- IT導入補助金で生産管理システムを導入し、生産性が20%向上
- ものづくり補助金で自動化設備を導入し、生産能力が50%向上
- 持続化補助金で展示会出展を行い、売上を30%拡大
サービス業B社
- 持続化補助金でホームページを開設し、オンライン集客を強化
- IT導入補助金でCRM・予約システムを導入し、顧客管理を高度化
- 上記で得た収益と新事業進出補助金でオンライン事業を立ち上げ、新たな収益源を確保
成長ストーリーの描き方(5年モデル)
- 1〜2年目:IT導入補助金・持続化補助金で基盤整備
- 3〜4年目:ものづくり補助金で設備投資・人材強化
- 5年目以降:新事業進出補助金で新事業分野に展開
中長期的な視点と、PDCAを意識した計画的な補助金活用が、持続的な企業成長のカギとなります。
第6章 まとめ:補助金は目的と相性で選ぼう
補助金選択の四つの判断軸
- 目的の明確化:短期の資金調達か中長期の成長投資か、設備・人材・販路のどこを優先するかを定義する。
- 時期の適切性:申請時期と事業実施時期を合わせ、資金需要や他制度との連携を考慮する。
- 体制の整備状況:社内の書類作成体制や専門家サポート、事業実施管理体制を確認する。
- 予算とリソースの現実性:自己負担額や必要人員、報告対応力を冷静に見極める。
よくある失敗と成功企業の共通点
補助金があるから申請するという補助金ありきの発想では、事業と制度がかみ合わず採択後の運営も困難になります。
成功している企業は、明確な成長ビジョンを前提に補助金を手段として位置づけ、外部専門家と連携しながら継続的に事業を改善・発展させています。
次に取るべき三つのステップ
- 情報収集の体系化:最新の公募要領や採択事例を集め、自社の業界・地域での活用実績を調査する。
- 専門家相談の活用:中小企業診断士、税理士・会計士など複数の専門家に相談し、費用対効果を検討する。
- スケジュール検討と準備:申請3か月前から準備を始め、2か月前に事業計画の骨子を固め、1か月前に書類を完成させる。社内で担当者を決め、情報共有体制と意思決定プロセスを整備しておく。
補助金はやりたいことを実現するための手段です。 目的に合致した制度を選び、計画的かつ継続的に活用することで、返済不要の資金をてこに持続的な企業成長を目指しましょう。
LINE公式アカウント始めました
WellFlagsではLINE公式アカウントで補助金情報、各種制度の発信を行っています! 登録特典もありますので、ぜひこちらからお友達登録をお願いします!

本日はものづくり補助金について最新情報をまとめました。
各種補助金についてのお問い合わせは上記LINEやお問い合わせフォームからお願いします!
それでは次回の記事もお楽しみにしていてください!

早稲田大学卒業後、大手総合商社に勤務し、
企業成長と多様な働き方の両立を支援する株式会社WellFlagsを設立
ものづくり補助金やIT補助金等の補助金申請代行の専門家として、各種補助金のコンサルタント、申請代行を実施
高い採択率を誇る補助金申請プロサポートの代表コンサルタントとしても活動中